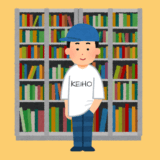エル
エル
 リミナ
リミナ
 エル
エル
Contents
逮捕された後の流れは?(フロー図で解説)
何らかの容疑で警察に逮捕され、刑事事件の容疑者(法律用語では被疑者といいます)となった場合、逮捕後はどのような流れで進むのでしょうか?
このページでは、逮捕された後の流れについて解説をしますが、まずはじめに、逮捕後の流れを簡単に図で解説します。
- 1.警察署での取り調べ
警察署に連行された容疑者は、警察官による取り調べを受けることになります。ここでは、弁解録取書と身上経歴供述調書という2種類の供述調書が作成されます。 - 2.検察への送検
警察から検察への送検がされた場合、容疑者を受けとった検察官は、24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断することになります。 - 3.勾留
逮捕後に身体拘束をされる期間は最大72日でしたが、勾留期間はこれに比べると長くなっており、原則10日間以内、延長された場合は最大20日続くことになります。 - 4.起訴・不起訴の決定
検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。起訴になった場合は刑事裁判となり、不起訴となった場合には前科がつくことなく釈放されます。 - 5.起訴状の提出
起訴をする場合、検察官は裁判所に、「被告人を特定できる事項」「公訴事実」「罪名」の3つを記載した起訴状を提出します。 - 6.刑事裁判
刑事裁判では、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論といった手続きを経て、判決が下されることになります。
 リミナ
リミナ
 エル
エル
逮捕された後の72時間とは?
刑事事件の容疑者として逮捕された場合、まずどのような手続きから始まるのでしょうか?
ちなみに、逮捕には、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「準現行犯逮捕」「緊急逮捕」の4種類があるのですが、逮捕された後の手続きはほとんど同じです。
 逮捕には4種類ある?
逮捕には4種類ある?警察署での取り調べ
逮捕されると、まずは警察署に連行されて、指紋の採取や写真撮影をされ、指紋のデータは警察にその後も残ることになります。
その後、警察署に連行された容疑者は、警察官による取り調べを受けることになります。ここでは、弁解録取書と身上経歴供述調書という2種類の供述調書が作成されます。弁解録取書は、容疑の内容に対する容疑者の弁解を記載するもので、身上経歴供述調書は容疑者の出身地・経歴などを記載するものです。
これらの供述調書は有罪の証拠にもなる可能性もあります。そのため、逮捕直後のパニックになってしまっている状態で不用意な発言をさけるためにも、弁護士と相談してから供述をするなどの対策が重要です。また、供述調書の内容に納得できない場合には、署名・捺印を拒否することもできます。
容疑者に逃亡の可能性があったり、証拠隠滅のおそれがあったりして、引き続き容疑者の身体拘束をする必要がある場合には、拘束をしたときから48時間以内に、調書などの書類や証拠と一緒に検察へ送検する必要があります。
刑事訴訟法203条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
検察への送検
警察から検察への送検がされた場合、容疑者を受けとった検察官は、24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断しなければなりません。
また、この判断は、容疑者の身体が拘束されてから72時間を超えることはできません。場合によっては、この24時間で起訴・不起訴の決定をする場合もあります。
身体拘束は、容疑者の人権を侵害することになりますので、刑事訴訟法で身体拘束をしておくことができる期間は厳しく定められています。
勾留請求を行うかどうかを判断するために、ここでも容疑者への取り調べが行われます。基本的には警察での取り調べと同様ですが、ここでは警察で作成された調書の内容確認を主に行うことになります。ここでも、弁護士と相談した上で取り調べを受けることと、納得できない内容である場合には署名・捺印を拒否することが重要です。
刑事訴訟法205条
検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
強引な取り調べをされた場合の対応
検察の取り調べではあまり起こりませんが、警察での取り調べでは現在でも強引な取り調べが行われる場合があります。たとえば、違法な長時間の取調べ、机を叩くなど威圧して自白をさせる、などという行為が考えられます。
このような違法な取り調べによって作られた供述調書は当然無効ではありますが、違法な取り調べがあった時点で弁護士に相談をすべきです。弁護士が検察官や警察署長などに、違法な取り調べをやめるよう申し入れを行うことで、このような取り調べをされることはなくなる可能性が高いです。
 リミナ
リミナ
 エル
エル
刑事事件を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用の相場については、下の関連記事で解説しています。
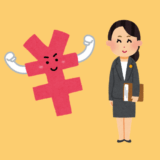 刑事事件の弁護士費用の相場は?
刑事事件の弁護士費用の相場は? 勾留とは?
勾留とは、逮捕された容疑者を、留置場や拘置所に拘束し続けるもので、検察官の勾留申請があった場合に、裁判官が勾留状を発行することで勾留をすることができます。
勾留できる条件
勾留することができるかどうかは、裁判官の判断によって決まります。そのときの判断基準は、「勾留の理由」「勾留の必要性」の2つがあるかどうかです。
「勾留の理由」とは、容疑者が罪を犯したことを疑うだけの証拠などがある上で、「容疑者に決まった住所がない」「証拠隠滅するおそれがある」「逃亡するおそれがある」のどれか1つに当てはまる場合に認められます。
勾留の理由がある場合でも、容疑者の体調・事件の重大性などから、容疑者の身体を長期間拘束することは適切でないと判断された場合には、「勾留の必要性」がないと判断され、勾留は認められないことになります。
刑事訴訟法60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
勾留期間は最大20日
逮捕後に身体拘束をされる期間は最大72日でしたが、勾留期間はこれに比べると長くなっており、原則10日間以内となっています。
さらに、検察官が申請し、やむを得ない理由があると裁判官が認めた場合には、更に10日間の延長をすることができます。つまり、勾留は最大20日続くということになります。
この勾留期間に、検察官は取り調べや証拠集めを行い、容疑者を起訴して裁判に持ち込むか、不起訴として釈放するかどうかを決定します。
刑事訴訟法208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
 リミナ
リミナ
起訴・不起訴の判断をされるとどうなる?
逮捕された後や勾留期間中に、検察官が容疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めると説明しました。それでは、起訴・不起訴の判断をするとどのようになるのでしょうか?
起訴された場合は刑事裁判へ
起訴とは、検察官が、捜査によって集まった証拠や取り調べなどから、容疑者が犯罪行為をした可能性が高く、刑事罰を受けるべきだと判断した場合に、裁判所に事件についての判断を求めることをいいます。
起訴をするかどうかを決めることができるのは検察官のみで、被害者がいくら起訴して欲しいと考えたとしても、検察官が起訴をするという判断をしなければ刑事罰を受けさせることはできません。ただし、被害者側がどうしても納得できない場合には、検察審査会に審査を申し立てることができます。
日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%といわれており、もし裁判まで進んだ場合には有罪となり、前科がつく可能性が高くなります。
そのため、刑事事件の容疑者として逮捕された場合には、起訴される前に早めの対応が重要です。
刑事訴訟法247条
公訴は、検察官がこれを行う。
罰金刑は略式起訴される場合もある
刑罰が100万円以下の罰金となるような、比較的軽微な犯罪では、容疑者の同意が得られた場合には、略式起訴という選択肢もあります。
略式起訴は、裁判と聞いて多くの方がイメージするような、裁判所で行う裁判ではなく、書類のみで手続きが進みます。そのため、通常の裁判よりも結論が出るのは早いです。
ただし、罰金刑であっても刑罰は刑罰ですので、前科がつくことにはなります。
刑事訴訟法461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。刑事訴訟法461条の2
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
不起訴になると前科がつかない
検察官が、容疑者が犯人である証拠が少ない、起訴する必要まではないなどのように判断した場合には不起訴処分となります。
不起訴処分には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
| 嫌疑なし | 容疑者に対する疑いが無くなった場合 |
| 嫌疑不十分 | 疑いはあるが、裁判において有罪の証明をする決定的な証拠はないような場合 |
| 起訴猶予 | 犯罪が軽微であったり、示談が成立していたりするケースなど、検察官の裁量によって不起訴とする場合 |
刑事事件で逮捕された場合に、不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。また、身に覚えのない罪で逮捕されている場合には、真犯人が別にいることを示す証拠などを用意する必要があります。
その上でさらに、検察官に対して不起訴処分が妥当であることを働きかける必要があります。刑事事件の経験などない一般人が自分で対処をすることは難しいので、弁護士への依頼が必要になってきます。
不起訴処分となると前科がつくことはなく、釈放され身柄も解放されることになりますので、容疑者側にとっての大きなメリットがあります。そのため、逮捕された場合には、不起訴処分獲得が1つの目標になります。
 リミナ
リミナ
 エル
エル
起訴から裁判までの流れは?
検察官が起訴をすると判断した場合、その後はどのように進むのでしょうか。
なお、ここからは、容疑者(被疑者)のことを、被告人と呼ぶようになります。
保釈制度を使用できる
起訴されることが決まったからといって、勾留が終了するとは限りません。裁判までの間に、逃亡したり証拠隠滅したりする可能性もありますので、引き続き身柄拘束をされる場合が多いです。被告人の勾留は、通常は検察官が請求するのではなく裁判所が行います。
起訴前の勾留は、最大で20日間と期限が定められていましたが、起訴後の勾留は2か月となっており、その後も必要があると認められれば1か月ごとの延長が可能で上限はありません。
刑事訴訟法60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。
裁判の手続きの間、2か月以上も勾留されることになると、被告人の心理的・肉体的な負担は相当大きくなります。そこで役に立つのが、保釈という制度です。
保釈とは、保証金の支払いなどを条件として、被告人が勾留から解放される制度で、起訴された後の被告人についてのみ認められ、起訴される前に保釈制度を利用することはできません。
保釈の請求があった場合には、重大事件や被告人の氏名が分からない場合など一定の場合を除いて、裁判所は保証金額を定めた上で、保釈を許さなければなりません(権利保釈)。また、裁判所が保釈すべきと考えた場合は、裁量で保釈することができ(裁量保釈)、拘束をあまりにも長くなった場合には保釈しなければなりません(義務保釈)。
保釈を請求する場合には、裁判所に保釈請求書と身元引受書を提出します。保釈金の相場としては、150万~300万円程度ですが、被告人の収入や事件の重大性などで金額は上下します。
保釈金は、被告人が出頭をしなかった場合には没収されるので、被告人がその金額を没収されたときのダメージも考慮して判断されることになります。たとえば、ライブドアの元社長であるホリエモンの保釈金は3億円というかなり高額な保釈金となりました。
 リミナ
リミナ
刑事訴訟法89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
(略)刑事訴訟法90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。刑事訴訟法91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
検察官が起訴状を提出
起訴をする場合、検察官は裁判所に起訴状という書類を提出します。起訴状には、「被告人を特定できる事項」「公訴事実」「罪名」の3つを記載しなければなりません。
「被告人を特定できる事項」とは、氏名、年齢、職業、住所など本人を特定できる情報のことです。
「公訴事実」とは、犯罪を構成する具体的な事実のことで、犯罪の日時、場所、方法などを具体的に書く必要があります。
「罪名」とは、裁判で適用されるべき条文のことです。ちなみに、ここでの公訴事実や罪名は、容疑の一部のみに絞ることもできます。これを、一部起訴といいます。
また、裁判官に余計な先入観を持たせることのないよう、被告人の前科、性格などを記載したり、別の書類として添付したりすることは禁止されています。
刑事訴訟法256条
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
検察官から裁判所へ起訴状が提出されたら、起訴状のコピーを裁判所は被告人に送り、その後、第1回公判期日が指定され、被告人に召喚状が送られることになります。
公判とは、公開された法廷で刑事裁判をすることをいいます。
刑事裁判の流れは?

裁判前に行うことができる手続き
裁判を円滑に進めるために、事前に行われる手続きとして証拠開示があります。証拠の多くは検察側が握っており、これを被告人側の弁護士などが確認することで、弁護の準備をすることができます。
証拠の開示については、裁判所が開示を命じることができるとされていますが、法律で定められた要件などはなかったため、公判前整理手続という制度が設けられました。公判前整理手続は裁判員裁判では必ず実施され、それ以外の事件では、弁護士や検察官の意見を裁判官が聞いて判断をします。
公判前整理手続では、検察官側、被告人側のそれぞれの主張とその証拠を開示した上で、争いとなる部分(争点)を整理します。そのため、この争点に集中してスムーズに裁判を進めることができるようになります。
公判前整理手続を行うことで、被告人側にメリットもデメリットもありますので、弁護士の判断に任せることになるでしょう。公判前整理手続に出席する場合には、悪い印象を持たれないようにすることが重要です。
刑事訴訟法316条の2
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
 エル
エル
冒頭手続
冒頭手続では、まず裁判長が被告人に氏名・住所・本籍などを確認し、本人であるかを確認します(人定質問)。
その後、起訴状を朗読し、被告人へ黙秘権があることの告知をします。そして、弁護人は、起訴状の内容に間違いがないか陳述を行います。
証拠調べ手続
冒頭陳述
証拠調べ手続は、証明責任を負う検察官が冒頭陳述を行うところから始まります。検察官の冒頭陳述では、これから証明しようとする事実と、どのように証明をするかについて明らかにします。
検察官の冒頭陳述の後、弁護人は冒頭陳述を行うことができます。これは強制的なものではありませんが、公判前整理手続が行われた裁判で、弁護人が証拠により証明しようとする事実がある場合には、弁護人の冒頭陳述が行われます。
証拠調べ請求
冒頭陳述が終わったあとは、検察官、弁護人は証拠調べ請求をします。
検察官の証拠調べ請求があった場合には、弁護人の意見を聞いた上で、証拠調べを行うかどうかを決定します(証拠決定)。弁護人が証拠調べ請求をした場合には、検察官の意見を聞いて証拠決定をします。
なお、自白を重視しすぎることは冤罪の原因にもなりますので、裁判外の自白については、自白以外の証拠調べが終わった後にしか証拠調べ請求をすることができません。
刑事訴訟法298条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
証拠調べ
証拠調べの方法は、証拠が「人」「書類」「物」のどれかによって変わってきます。
証拠が、証人など「人」の場合には、証人尋問を行います。証拠が「書類」の場合には、書類を朗読し、「物」の場合には、その物を見せることになります。
刑事訴訟法304条
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。刑事訴訟法305条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。刑事訴訟法306条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。
被告人質問
被告人が自分の意思で供述をする場合は、裁判官、検察官、弁護人などから被告人に質問をすることができ、ここでの被告人の供述も証拠となります。これを、被告人質問といいます。
弁論
証拠調べ手続きが終わると、次に弁論手続が行われます。
まずはじめに、検察官による論告が行われます。論告とは、検察官が犯罪の事実と法律の適用について意見を述べることをいいます。ここで、被告人にどのような刑罰を求めるかの求刑についての意見も述べられます。
その後、被害者参加制度が利用されている場合には、被害者が意見を言うことができます。
そして、弁護人の最終弁論が行われます。最終弁論では、無罪であることを主張したり、求刑が重すぎることや執行猶予をつけるべきと主張したりするなど、被告人に有利な判決が下るように主張することになります。
判決
最終弁論まで終わると、最後に判決が下されることになります。
判決は有罪・無罪があり、有罪の中でもすぐに刑が執行されることになる実刑判決と、刑の執行が猶予される執行猶予判決があります。
通常の裁判では裁判官が判決を行い、裁判員裁判では、裁判官と裁判員で構成される合議体が判決を行います。
検察官・弁護人のどちらか一方が、この判決に不満がある場合には、控訴をして高等裁判所での裁判を請求することもできます。
 エル
エル
逮捕されたら自分で弁護士を探せる?
刑事事件で逮捕された場合であっても、早めに示談を成立させるなどして不起訴処分を獲得したり、刑事裁判においてもしっかりと準備をすることで執行猶予などを勝ち取ったりすることができる可能性があります。
不起訴処分を獲得すれば前科がつくことはありませんし、執行猶予であれば刑務所に入らずに済みます。
このような有利な処分を勝ち取ることで、社会生活への復帰や更生をスムーズに行うことができる可能性も上がりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されたあとでは、外部との連絡をとることは難しくなりますので、逮捕されるかもしれないと考えている方はなるべく早く弁護士に相談するようにしましょう。もしも、身内が逮捕されてしまっている場合には、家族が刑事事件に強い弁護士に連絡をとることが重要です。
 リミナ
リミナ
刑事事件に強い弁護士のおすすめの探し方は下の関連記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
 刑事事件に強い弁護士の探し方 おすすめ10選
刑事事件に強い弁護士の探し方 おすすめ10選